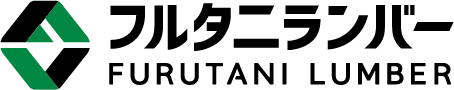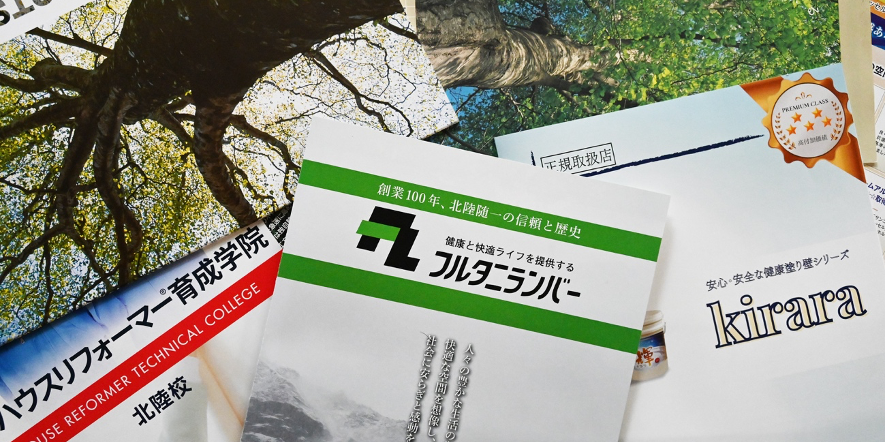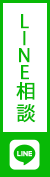フルタニランバー株式会社
コラム「森のフルタニさん」
クリーンウッド法とは?木材事業者が知っておくべき内容と対応のポイント
投稿日:2025.06.23/更新日:2025.06.26

違法伐採による森林破壊が深刻な環境問題となっている昨今、日本では「クリーンウッド法」の施行によって持続可能な木材利用の推進が進められています。
では、クリーンウッド法は木材関連事業者にとってどのような影響があるのでしょうか。
本記事では、クリーンウッド法が制定された目的や背景・制度の内容、とくに2025年4月の改正による影響ついて詳しく解説します。
あわせて、私たち木材関連事業者はクリーンウッド法に基づいてどのような対応をするべきなのかについても解説します。
森林を守り、法に則った木材売買をしたいと考えている木材関連事業者の方はぜひ参考にしてください。
Contents
クリーンウッド法とは

はじめに、クリーンウッド法が制定された目的や背景、概要について解説します。
クリーンウッド法が制定された目的と背景
クリーンウッド法は、正式には「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」という名称で、2017年に施行。
その後、2025年に改正クリーンウッド法として施行されました。
クリーンウッド法の目的は、違法伐採を厳格に処分することで自然環境の保護、木材産業の持続的かつ健全な発展を目指すことです。
違法伐採は、地球温暖化や森林の多面的機能、木材市場での公正な取引に悪影響を与える恐れがあるということが、法律が制定された背景にあります。
なお、2025年の法改正によって以下の内容が追加されました。
- 川上〜水際段階での合法性確認義務の明確化(第1種木材関連事業者)
・仕入木材の原材料情報収集
・合法性の確認
・記録の作成・保存
・次段階事業者への情報伝達 - 素材生産・販売事業者による情報提供義務
- 小売業者の対象追加と登録促進
- 対象物品の拡大と「主な部材」基準の見直し
- 罰則の導入と強化
この改正により、私たち木材関連事業者には自社の立場(素材生産販売・第1種・第2種・小売り)を明確化させ、在庫木材の合法性確認や情報整理・保存を厳格に行うことが求められます。
また、改正された法に準じた事業の運営体制を確立するために、取引先との情報伝達の方法整備や情報保存や伝達に向けたシステム整備も必要になります。
なお、この改正では違反時の罰則も設けられたため、木材関連事業者はクリーンウッド法をしっかり理解し、法に則った事業運営をすることがこれまで以上に重要になりました。
クリーンウッド法の制度内容と義務化された理由
クリーンウッド法の主な概要は以下のとおりです。
| 主な制度内容 | 概要 |
| 合法性の確認 | ・合法に伐採された木材かを確認する責任 ・原材料の出所や関連書類の収集、確認、記録 |
| 登録制度 | ・登録事業者となることで合法の事業者であると訴求できる ・登録は任意(第1種事業者は実質的に義務化) |
| 情報の伝達・記録 | ・仕入れ、販売時に合法性確認情報を取引相手へ伝達 ・書面などにより一定期間の保存が必要 |
また、クリーンウッド法の義務化には以下のような理由が挙げられます。
- 違法伐採の抜け道を防ぐ
- 違法伐採の対策が進んでいる国際社会との足並みを揃え、信頼を確保する
- サプライチェーンの透明化
- ESG※1、CSR※2への対応と企業価値の向上
- 変化した消費者ニーズへの対応(合法性の情報の可視化)
※1:「Environment(環境)・Social(社会)・Governance(ガバナンス)」の略。企業の長期的な成長や持続可能性を評価するための基準。
※2:「Corporate Social Responsibility」の略。利益追求だけでなく社会や環境への配慮を持って行動する責任。
関連記事:FSC®認証の費用は無料?メリットや取得方法を簡単に解説
クリーンウッド法に基づく登録制度とは

クリーンウッド法の登録制度は、木材関連事業者が「合法伐採木材の利用を促進する体制がある」と登録することで、公的な証明ができる制度です。
登録制度の仕組みや役割、申請の流れについて解説します。
登録制度の仕組みと役割
クリーンウッド法の登録制度は、基本的に任意となっていますが、第1種木材関連事業者の登録は実質的に義務に近いです。
事業者としての登録を促すことで流通する木材の流れを把握し、違法伐採の防止を図ります。
木材事業者側は、登録をすることで信頼性の向上や取引拡大・CSRの強化などのメリットを得ることができます。
登録申請の流れと必要な書類
登録申請の主な流れは、以下のとおりです。
- 登録実施機関へ事前相談をする
- 申請書類の作成・提出・手数料の支払い
- 審査後、登録の可否が通知される
登録の申請に必要な書類は複数あるので、登録する前に不備がないか確認をするとスムーズです。
- 登録申請書
- 誓約書
- 違法罰則に関する宣誓書
- 法人関係書類(法人の場合)
- 会社概要、組織図
- 登録免許税の領収書(コピー)
- 社内体制、手順書
法人の場合、定款や登記事項証明書・役員名簿などが必要になります。
登録をする際は早めに準備しておきましょう。
また、登録には新規登録手数料や更新料・年会費なども必要になります。
クリーンウッド法の対象となる木材関連事業者

クリーンウッド法の対象となる事業者は、「素材生産販売事業者」と「木材関連事業者」に分類されています。
それぞれの概要を解説します。
素材生産販売事業者
素材生産販売事業者は、以下の2点に該当する事業者が対象となります。
- 所有する樹木について、譲渡し先等を自ら決定する樹木の所有者
- 樹木の所有者から、当該樹木の譲渡し先等の決定を委ねられた事業者
なお、伐採のみを行う事業者や日本における法人格をもたない海外事業者は対象外となっています。
第1種・第2種木材関連事業者
木材関連事業者は、第1種と第2種に区分され、概要は以下のとおりです。
| 第一種木材関連事業者 | 国内で最初に木材の譲受を行う事業者 |
| 第二種木材関連事業者 | 第一種以外の木材関連事業者 |
関連記事:有機JAS認証は木材にも適用される?取得の流れや費用を解説
事業者がクリーンウッド法に基づいてとるべき対応
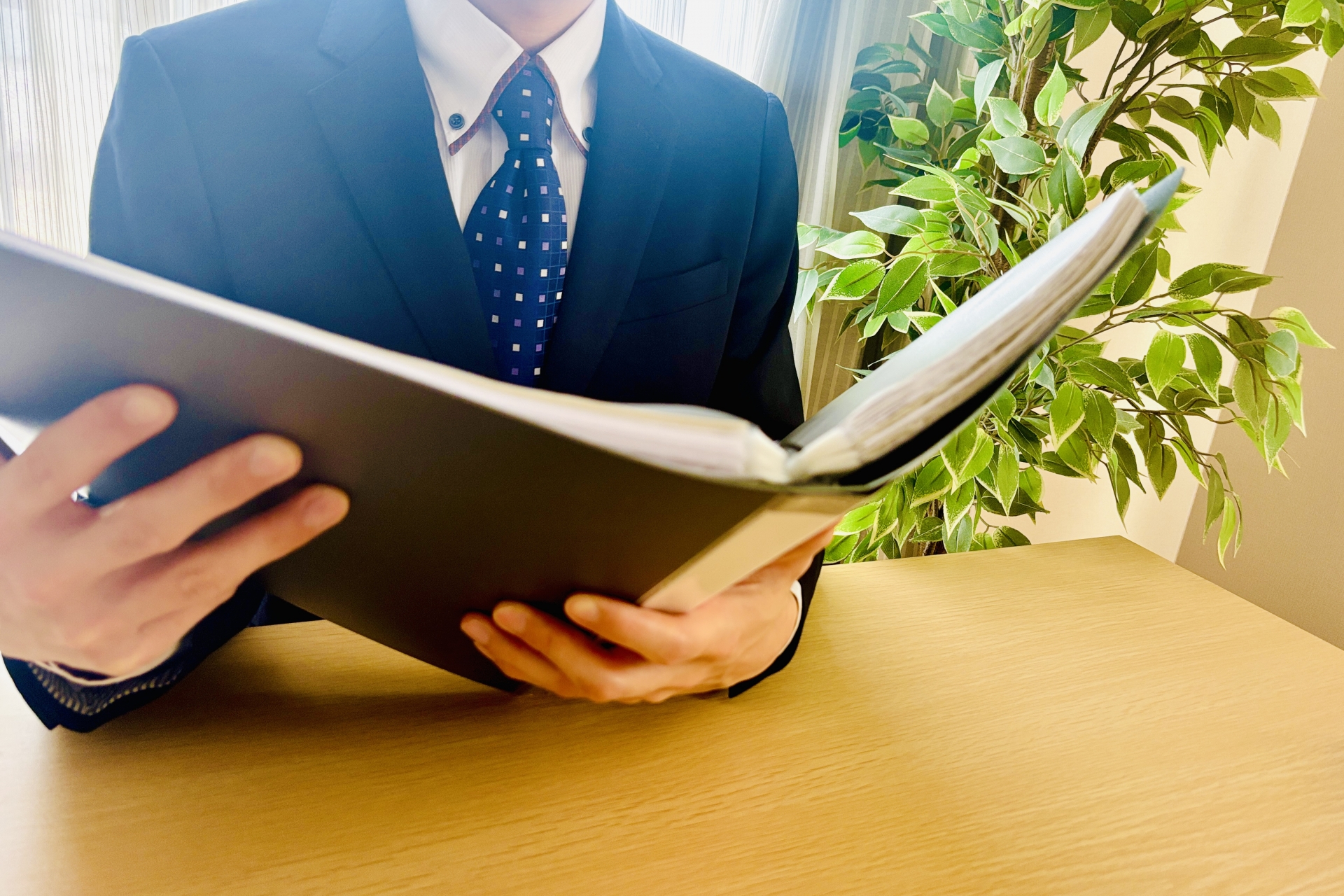
クリーンウッド法が施行されたことで、各関連事業者は法律に則った対応が求められるようになりました。
事業者ごとのとるべき対応を解説します。
素材生産販売者の場合
木材を伐採し丸太(原木)として販売をする素材販売生産事業者は、販売先である第1種木材関連事業者の求めに応じて、山地や合法性などの必要な情報の提供をする義務が生じます。
第1種木材関連事業者の場合
第1種木材関連事業者に求められる対応は以下のとおりです。
| 義務 | ・原材料情報の収集、整理 ・合法性の確認 ・記録の作成、保存 ・情報の伝達 ・定期報告 |
| 努力義務 | 体制の整備など、合法伐採木材等の利用を各日するための措置 |
第2種木材関連事業者の場合
第1種木材関連事業者以外が該当する第2種木材関連事業者は、以下に挙げる内容に対して努力義務が課せられています。
【努力義務】
- 第一種木材関連事業者からの情報の受取・保存
- 消費者等への情報の伝達
- 体制の整備など、合法伐採木材等の利用を各日するための措置
クリーンウッド法の対象となる物品

クリーンウッド法の登録に該当する事業者とその対応について解説してきましたが、対象となる物品も、法によって定められています。
木材
木材という言葉だけでは広義的に捉えられがちですが、クリーンウッド法では以下のように定義されています。
- 素材:丸太、枝葉、根株、林地残材、風倒木処理等の伐採に類する行為 により生産されたもの等を含む
- 板材、角材及び円柱材:化学的又は物理的な処理により密度・硬度等を増加させたものを含む
- 単板、突き板及び構造用パネル(OSB)
- (1)と(3)又はこれらに類するものを接着等して製造されたもの
(合板、単板積層材、集成材、直交集成板、たて継ぎ等)DLT、NLT等の接着剤を使用せずに接合したものや
I 型複合梁を含む - のこくず・木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状等の形状に凝結させてあるか否かを問わない)、
チップ及び小片端材
木材等(家具・紙等の物品)
家具や紙類など、木材によって作られた製品として、以下のものが該当します。
- 椅子、机、棚、収納用じゅう器、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、
ホワイトボード及びベッドフレームのうち、主たる部材に木材を使用したもの - 木材パルプ
- コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、塗工されていない印刷用紙、
塗工されている印刷用紙、ティッシュペーパー及びトイレットペーパーのうち、木材パルプを使用したもの - フローリングのうち、基材に木材を使用したもの
- 木質系セメント板
- サイディングボードのうち、木材を使用したもの
- 戸(主たる部材に木材を使用したものに限る。)及びその枠(基材に木材を使用したものに限る。)
- (1)~(7)の物品の製造又は加工の中間工程で造られたものであって、
以後の製造又は加工の工程を経ることによって当該物品となるもののうち、
木材又は木材パルプを使用したもの
関連記事:家具や木造住宅に使用される人気の木材の種類一覧やそれぞれの特徴
クリーンウッド法に違反した場合の罰則

2025年の法改正により、クリーンウッド法に違反した場合は、いくつかの段階があるものの、最終的には以下の厳格な罰則が定められています。
| 違反行為 | 罰則 |
| 合法性確認を怠る | 100万円以下の罰金 |
| 情報提供義務違反 | 100万円以下の罰金 |
| 虚偽申告・虚偽報告 | 30万円以下の罰金 |
| 違反の反復(繰り返し違反をする) | 最大で300万円以下の罰金 |
上記以外にも、監督官庁による指導・勧告・公表といった罰則も設けられており、場合によっては事業者登録の取り消しがされる可能性もあります。
まとめ(フルタニランバーでの対応)
クリーンウッド法により、関係する事業者はさまざまな対応が求められるようになりました。
しかし、この法律は木材という天然資源を守り、持続可能な木材利用をするために重要な役割を担っています。
違法伐採をなくすことで、自然環境を保護し、また関連する木材事業者の社会的責任を向上することも可能になります。
木材関連事業者の方はクリーンウッド法を遵守し、透明性のある取引で事業を続け、消費者にとって安心で安全な素材の提供をしていきましょう。
フルタニランバーでは社内コンプライアンス体制の整備と合法確認体制を強化しています。
各仕入れサプライチェーンと社内の仕入れ担当者への研修を行うなど勉強とそれに伴う対応を実施しています。
合法性が証明された材の取り扱いと販売を今後も心掛けていきますので、是非お気軽にお問合せください。